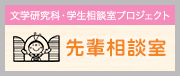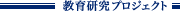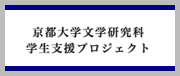- HOME
- 日本哲学史専修ホームページ
- 思想家紹介 三木清
思想家紹介 三木清
三木 清 1897-1945(明治30-昭和20)

略 歴
1897年兵庫県生まれ。一高在籍時に、西田幾多郎の『善の研究』に強い感銘を受け、京大で哲学を学ぶことを決心する。当時一高を出て京大に進むことは極めて異例であった。この後、戸坂潤や西谷啓治、梯明秀など多くの俊英がこのコースをたどることとなった。
1922年からドイツに留学。当初ハイデルベルク大学のリッケルトの下で学んでいたが、翌1923年マールブルク大学に移りハイデガーから強い影響を受ける。さらに1924年フランスに移住。ハイデガーから学んだ解釈学的手法を駆使して、パスカル『パンセ』についての論文をパリの下宿で書き、『思想』に投稿。この論文がもととなり、処女作『パスカルに於ける人間の研究』が出版される(1926年)。
1927年、法政大学の哲学科の教授に赴任。この時期から三木は人間学を基礎とした独自のマルクス解釈を展開し始める。論文「人間学のマルクス的形態」などが収められた『唯物史観と現代の意識』を1928年に刊行。マルクス主義を哲学として理解するという三木の試みは日本近代思想史上画期的な出来事であり、当時の日本の思想界に大きな反響を呼んだ。しかし、1930年に日本共産党への資金援助の嫌疑で検挙・拘留され、法政大学での職を退くことを余儀なくされる。
出所後の三木は多方面にわたって精力的な活動を行なっていく。1932年には『歴史哲学』を刊行。未定稿に終わったが『哲学的人間学』が執筆され始めたものこの時期にあたる。また、哲学的論稿・著作を発表すると同時に批評家としても活躍。1931年の満州事変の勃発を契機として日本の時代状況が暗転していく中で、「不安の思想」を新しいヒューマニズムによって超克することを試み(「不安の思想とその超克」(1933年)など)、時局に対する評論活動を積極的に展開する。さらには、「岩波講座哲学」、「岩波新書」などの立ち上げに尽力するなど文化人としても活躍。1937年に日本が中国との全面戦争に突入したことを背景として、三木は近衛文麿の政策集団である「昭和研究会」に参加。そこで指導的な役割を果し、東亜共同体論を展開していくこととなる。
三木はアカデミズムの枠をこえて積極的に時代と関わっていきながらも、哲学研究に対する意欲は旺盛であり、晩年には多くの哲学的著作が発表されている。1939年、『構想力の論理 第一』を出版。その続編である論文「経験」は同年から1943年にわたって『思想』に掲載され、三木の死後『構想力の論理 第二』として1946年に出版されている。この未完の『構想力の論理』が三木の主著であると言ってよい。また、『哲学入門』を岩波新書の一冊として刊行(1940年)。これは、三木哲学への入門書であると同時に西田哲学への最良の入門書である。その他には、『人生論ノート』(1941年)や『哲学ノート』(1941年)・『続哲学ノート』(1942年)、『技術哲学』(1942年)などがある。
しかし、1945年6月12日、治安維持法の容疑者をかくまったという嫌疑により検挙・拘留される。戦争終結後の1945年9月26日、豊多摩拘置所で疥癬(カイセン)の悪化により獄死。享年48歳。この三木の非業の死をきっかけとしてGHQは治安維持法を撤廃したとされている。残された遺稿は『親鸞』であった。
思 想
三木清の哲学は実に多彩な側面を持っている。歴史哲学、人間学、宗教論、”唯物論”、等々、様々な角度から三木の哲学を特徴付けることが可能であろう。多様な変転をとげる三木の思索に一貫して流れているのは、三木自身が好んで用いた表現を借りれば、ロゴス的なものとパトス的なものをめぐる問いである。論理的な把握からはこぼれ落ちるパトス的なものを、いかにしてロゴス的なものに至らしめるのか、三木が生涯問い続けたのはこの問題であったということが出来るであろう。パトス的なものといっても、三木においてそれは単に個人の内面性にとどまるものではない。それは存在そのものの非合理性を意味している。また、ロゴス的なものといっても、それは対象的論理を指しているのではなく、存在の非合理性が合理性へともたらされる構造性、いわば存在の自己表現のあり方を意味している。パトス的な深淵に沈潜して言説を放棄するのではなく、あくまでもそれにロゴス的な表現を与えようとしたところに三木の哲学の魅力があると言ってよいだろう。
・『パスカルに於ける人間の研究』
処女作『パスカルに於ける人間の研究』においては、パトス的なものは不安の内にあって揺れ動く人間的生として描き出されている。三木によれば、人間の存在は宇宙全体に対しては取るに足らない微小な存在であるが、同時に虚無に比すれば一個の世界であり全体である。このような人間的生を三木は全体と虚無との中間的存在として捉える。パスカルのいう人間の「偉大さ」と「惨めさ」は、この全体と虚無の間にあって絶えずさまよう中間者としての人間的生の構造にその根拠をもつ。この中間者としての人間という思想が三木の人間学の基底をなしており、またそれは遺稿『親鸞』に至るまで三木に一貫して流れている人間観であったと言える。
・「人間学のマルクス的形態」
パトスとロゴスをめぐる問題は、三木がマルクス主義の人間学的基礎付けを試みていく時期においてより明瞭なかたちとなって現われてくる。ここにおいて三木はパトス的なものを「基礎経験」という言葉で表現している。それは、ロゴスの支配から自由であり、却ってロゴス的なものがそこから生産されていく根源的な経験を意味している。そしてこの際に特徴的なことは、三木はロゴス的なものとしてイデオロギー(第二次のロゴス)と同時にアントロポロギー(人間学/第一次のロゴス)を想定し、「基礎経験」がイデオロギーへと至るのはあくまでもこのアントロポロギーを介してであるという構造を解明していることである。したがって、イデオロギーとしてのマルクス主義、唯物史観の内においても、「基礎経験」に裏打ちされた”人間とは何であるのか”という人間学的問いが秘められているということになる。これが三木の提示したマルクス像であった。この三木の主張は、マルクス主義と哲学の間に通路を切り開いたものとして極めて重要な思想史的意義をもっているといえる。西田幾多郎や田辺元などが積極的にマルクスを問題としたのも、この三木の議論に影響するところが大きいと考えられる。
・『歴史哲学』
ところで、三木が「基礎経験」と規定したパトス的なものには、存在の歴史性が含意されている。この問題を積極的に展開したのが『歴史哲学』である。通常歴史の概念は、その言葉の二義性から、叙述された歴史(「ロゴスとしての歴史」)と出来事としての歴史(「存在としての歴史」)とに区別されて考えられているが、ここで三木はそれらに加え新たに「事実としての歴史」という概念を提示する。それは端的に言って、歴史の「基礎経験」であり、出来事としての歴史の根底に存しそれを生み出すところの「原始歴史」である。
そして三木は、この「事実としての歴史」という概念において行為の立場を明確に打ち出している。三木によれば、「事実」(Tat-sache)とは、「行為」(Tat)と「物」(Sache)が直ちに一つであるということを意味している。このように歴史の根源性を行為に求めるといっても、三木において行為は単なる主体の倫理的決断でもなければ、<主―客>の分離を前提とした主体の客体への働きかけでもない。行為は常に「物」と切り離すことが出来ないというのが三木の洞察である。このように言えるのは、行為的自己がとりもなおさず身体的・感性的自己であるからだと三木は考える。しかも、そのような自己における行為が歴史の根源性であるのは、我々の身体が単なる個人的な身体ではなく既に「社会的身体」としての性格を持っていることによるというのが三木の考えである。ここに三木は歴史におけるパトス的なものを見ている。
・『構想力の論理』
三木のこのようなロゴスとパトスをめぐる思索、あるいは存在の合理性と非合理性をめぐる問題は、大きく言えば当時の日本の哲学者に共有されていたものであったと考えられる。ロゴス的把握からは常に漏れ出ていてこれに逆らい続けるもの、ロゴスの圏域を越えたもの、これをいかにして語るのかという問題に肉迫したのが、西田幾多郎の「絶対無の場所」であり、田辺元の「絶対媒介の論理」であり、あるいは九鬼周造の偶然性をめぐる思索であったと言うことが出来るだろう。これらの哲学者の中にあって三木の哲学の独自性が主張されるのは、この問題に迫るための立脚点を三木が具体的に構想力に求めたという点である。このことが展開されているのが『構想力の論理』である。
ここにおいて三木はそれまでのロゴスとパトスをめぐる問題を、ロゴスとパトスの統一の問題として明確化している。そして、カントが構想力に両者全く異質な感性と悟性を結合する機能を認めたことを念頭に置きながら、この概念を拡張し、それを歴史的場面においてロゴスとパトスとを結合する”歴史の”構想力として捉えようとしている。
また、このような「構想力の論理」は三木においては同時に「形の論理」として考えられている。これによって歴史は形から形への変化、メタモルフォーゼであると主張される。さらに三木は、自然も技術的であり「形」を作るとして、自然の根底にも「形」を想定し、自然史と人間史を構想力の論理によって統一するという壮大な試みを提示している。
このような「形の論理」を可能にするものとして三木が強調するのは制作(ポイエーシス)的行為の立場である。しかし、制作といっても単に芸術的活動を意味する狭い概念ではなく、広く人間の行為が「形」に働きかけそれを作り変えていく能力として理解されている。
このような「形の論理」、制作的行為の立場は、三木自身が認めているように極めて西田哲学に近いものである。このことは三木が自らの「構想力の論理」を「行為的直観」の立場に立つものとしていることからも明らかである。しかし同時に三木は、西田の「行為的直観」を「心の技術」にとどまるものとして観想的立場に陥る危険性を有していることを指摘している。このことから三木がこの『構想力の論理』において西田哲学の具体化、乗り越えを試みていたと推測できるかもしれない。しかし、もしそうであるとすれば、果たしてそれはどのような意味においてなのか。この問題は現在においてもさらなる解明が必要とされる問題であるということが出来よう。また、遺稿『親鸞』がこの『構想力の論理』とどのようにつながるのかという問題についてもそうである。三木の哲学において残された問題は多い。
『構想力の論理』は三木の死によって未完のままで終わっている。上に挙げた問題もこのような制約によるところが大きい。しかし、そうであるからこそ却ってこの『構想力の論理』は我々の”想像力”を刺激する魅力的な書であるとも言えるだろう。未完の三木哲学をいかに発展・継承していくのかということは我々に残された大きな課題である。
テキスト
A. 全集、著作集
- 『三木清全集』(全19巻)、岩波書店、1966-1968年
- 『三木清全集』(全20巻)、岩波書店(1986年に第20巻が新たに追加されたもの)
- 『三木清著作集』(全16巻)、岩波書店、1946-1951年
B. 文庫・新書で読める三木の著作
- 『人生論ノート』、新潮文庫、2000年
- 『語られざる哲学』、講談社学術文庫、1977年
- 『哲学入門 改版』、岩波新書、1976年
- 『パスカルにおける人間の研究』、岩波文庫、1980年
C.三木の著作が再録されている単行本
- 『三木清エッセンス』(内田弘 編・解説)、こぶし書房、2000年
- 『パスカル・親鸞』〔京都哲学撰書〕(大峯顯解説)、燈影舎、1999年
三木の宗教論が主に収められている。処女作『パスカルに於ける人間の研 究』、遺稿『親鸞』所収。 - 『創造する構想力』〔京都哲学撰書〕(大峯顯解説)、燈影舎、2001年
三木の主著である『構想力の論理 第1』、『構想力の論理 第2』が収め られている。
その他のものとして
- 『三木清』〔現代日本思想体系33〕(久野収編)、筑摩書房、1966年
- 『三木清集』〔近代日本思想体系27〕(住谷一彦 編・解説)、筑摩書房、1975年
参考文献
A. 三木の哲学に関する研究書(現在入手しやすいものとしては以下の三つが挙げられる)
- 赤松常弘『三木清――哲学的思索の軌跡』、ミネルヴァ書房、1994年
- 唐木順三『三木清・無常』(松丸壽雄編、京都哲学撰書第26巻)、燈影舎、2002年
- 内田弘『三木清――個性者の構想力――』、御茶の水書房、2004年
その他の重要な研究書として
- 宮川透『三木清』〔UP選書〕、東京大学出版会、1970年
- 荒川幾男『三木清―哲学と事務の間』、紀伊国屋書店、1981年
B. 「京都学派」の哲学との関係で三木の哲学を解明しているものとして
著者それぞれの観点から、三木の思想と「京都学派」の哲学者との関連性が描き出されており興味深い。
- 舩山信一『日本哲学者の弁証法』(服部健二 編・解説)、こぶし書房、 1995年
生前の三木と親交のあつかった著者による研究書。書名の通り、日本の哲学者 の哲学を弁証法という観点から取り扱っている。著者によれば、西田幾多郎が 「場所の弁証法」、田辺元が「媒介の弁証法」、高橋里美が「全体の弁証法」であるの に対して、三木は「形の弁証法」とされている。 - 小坂国継『西田幾多郎をめぐる哲学者群像――近代日本哲学と宗教――』、ミネ ルヴァ書房、1997年
西田哲学と日本の哲学者との関わりを中心に、田辺元、高橋里美、三木清、 和辻哲郎、久松真一が取り上げられている。西田哲学と三木の哲学との比較がな されており、遺稿『親鸞』の分析も詳しい。 - 服部健二『西田哲学と左派の人たち』、こぶし書房、2000年
これまであまり取り扱われてこなかった「京都学派」の左派に光をあてた著作。 三木清と梯明秀、舩山信一との思想的交流が描き出されている。また、三木の時 局との関わりについての分析も試みられている。 - 田中久文『日本の「哲学」を読み解く』、ちくま文庫、2000年
現在最も安価で入手できる日本哲学への入門書。西田哲学における「無」の概 念を独自の仕方で展開させていった哲学者として、和辻哲郎、九鬼周造、三木清 の哲学が取り上げられている。
C.三木清に関するエピソードが収められたものとして
- 竹田篤司『物語「京都学派」』、中公叢書、2001年
- 梯明秀『全自然史的過程の思想』、創樹社、1980年
ここに収められている「座談会・京都哲学左派の形成過程」(梯明秀、坂田吉 雄、船山信一、甘粕石介、上山春平が参加)は三木のひととなりがわかるのもと して興味深い。 - 『回想の三木清』、三一書房、1948年
D. 三木に関する論文を収めたものとして
- 『日本近代思想を学ぶ人のために』(藤田正勝編)、世界思想社、1997年
―― 服部健二「人間の歴史的生―三木清―」 - 『日本の哲学を学ぶ人のために』(常俊宗三郎編)、世界思想社、1998年
―― 丸山高司「構想力の論理―三木清―」 - 『京都学派の哲学』(藤田正勝編)、昭和堂、2001年
- 『日本の哲学 第2号』(日本哲学史フォーラム編)、昭和堂、2001年
―― 岩城見一「<仮説概念>としての<構想力>――その理論的意義と受 容」
―― 田中久文「虚無からの形成力――三木清における「構想力」論」 - 『京都学派の思想――種々の像と思想のポテンシャル』(大橋良介編)、人文書院、 2004年
―― 服部健二「「京都学派・左派」像」
―― 秋富克哉「技術思想――西田幾多郎と三木清」
―― 赤松常弘「三木清の哲学」
| Copyright © 2004 京都大学大学院文学研究科日本哲学史研究室 |