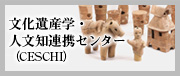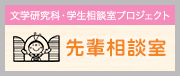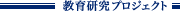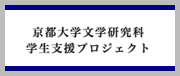京都大学文学部百年のあゆみ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以下の記述は2006年6月10日発行の時点のものです。)
1 文科大学期(1906~1919年)
文科大学の創設
京都大学文学部の誕生は1906(明治39)年6月4日、勅令第135号によって京都帝国大学文科大学の開設が定められた時にさかのぼる。京大に法科大 学・医科大学・理工科大学と並んで文科大学を置くことは、京大を2番目の帝国大学として設立することを定めた1897年6月制定の勅令第209号にすでに 定められていた。1898年から翌々年にかけて教授就任予定者たち(大西祝・松本文三郎・谷本富・狩野直喜)が海外留学に派遣され、開設に向けた準備は早 くから進められていた(大西は文科大学学長に予定されていたが、病気のため実現しなかった)。にもかかわらず実際の開設が他の分科大学に比べて遅れたの は、東京帝国大学の文科大学さえ学生定員を満たしていないのだから開設を急ぐ必要はないとする文部省の一部の意向や、日露関係の緊迫といった状況のゆえと 伝えられている。
とはいえ日露戦争終結後の1905年11月には設立案が帝国議会を通過し、翌1906年4月に狩野亨吉(第一高等学校校長)・谷本富(京都帝大理工科大学 講師)・狩野直喜(台湾旧慣調査会)・松本文三郎(東京帝大文科大学講師)・桑木嚴翼(第一高等学校教授)の5名が開設委員に任命されてようやく創立の準 備が整った。次いで6月には勅令135号によって当初設置される6つの講座が定められ、文部省令第10号によって9月11日に文科大学を開設することが決 まった。7月には上記の開設委員に松本亦太郎を加えた6名が相次いで教授に就任、狩野亨吉が初代文科大学学長に就任した。8月16日に最初の文科大学規程 が制定され、哲学・史学・文学の3学科を置くことや各学科に属する正副の科目の種類などが定められた。9月3日には最初の教授会が開催され、9月25日か ら授業が開始された。
初年度の入学者は本科学生16名、選科生徒19名であった。もっとも初年度に開講されたのは哲学科のみであり、講座の設置と教官人事が進むのに応じて史学 科は翌年、文学科は翌々年と1年ずつ遅れて授業が始まった。当初のスタッフはいずれも当時30歳台から40歳台初めの若さであり、大半は東大出身者であっ たが、内藤虎次郎(湖南)・幸田成行(露伴)・米田庄太郎らの採用に見られるような経歴にこだわらない人事も行われた。実現こそしなかったものの、高山林 次郎(樗牛)や夏目金之助(漱石)もそれぞれ美学と英文学の教授に予定されていた。外国人を当初から外国文学の教授に採用しなかったのも京大文科大学の特色である。
表1 文科大学の講座設置年度
| 学科 | 講座 | 1906 (明治39) |
1907 (明治40) |
1908 (明治41) |
1909 (明治42) |
1912 (明治45) |
1916 (大正5) |
| 哲
学 |
哲学・哲学史第一 (哲学・西洋哲学史) |
○ | |||||
| 哲学・哲学史第二 (印度哲学史) |
○ | ||||||
| 哲学・哲学史第三 (支那哲学史) |
○ | ||||||
| 哲学・哲学史第四 (西洋哲学史) |
○ | ||||||
| 心理学 | ○ | ||||||
| 倫理学 | ○ | ||||||
| 教育学・教授法 | ○ | ||||||
| 宗教学 | ○ | ||||||
| 社会学 | ○ | ||||||
| 美学・美術史 | ○ | ||||||
| 史
学 |
国史学第一 | ○ | |||||
| 国史学第二 | ○ | ||||||
| 東洋史学第一 | ○ | ||||||
| 東洋史学第二 | ○ | ||||||
| 東洋史学第三 | ○ | ||||||
| 史学・地理学第一 (西洋史学) |
○ | ||||||
| 史学・地理学第二 (地理学) |
○ | ||||||
| 史学・地理学第三 (西洋史学) |
○ | ||||||
| 考古学 | ○ | ||||||
| 文
学 |
支那語学・支那文学 | ○ | |||||
| 西洋文学第一 (独逸文学) |
○ | ||||||
| 西洋文学第二 (英文学) |
○ | ||||||
| 国語学・国文学 | ○ | ||||||
| 言語学 | ○ | ||||||
| 梵語学・梵文学 | ○ |
講座編成と教育課程の特徴
創立から4年の間に合計23講座が集中的に設置され、戦後にまで続く講座編成の骨格がほぼ固まった(表1参照)。当時の東京帝大文科大学と比べて、そこに は次のような特徴が見出される。(1)東大では論理学・倫理学と一緒になっていた心理学を独立の講座としたこと、(2)東洋学が重視され、東大では漢学科 にまとめられていた支那哲学・東洋史学・支那文学が3学科に分離して置かれたこと(とりわけ東洋史学は最初から3講座と破格の扱いであった)、(3)地理 学を独立の講座として史学科においたことなどである。
文科大学規程に定められた教育課程は次のようなものであった。まず各学科に正科目と副科目が指定され、正科目は普通講義・特殊講義・演習からなる。学生は 自分の所属学科のすべての正科目の普通講義を履修したうえ、正科目の1つを専攻科目として選択してその特殊講義と演習を履修することが義務づけられた。副 科目は自由選択である。普通講義は1回生、特殊講義は2回生以上、演習は3回生のときに履修するのが原則とされる。入学後1年目の学生は学科に分属するだ けで、2年目に専攻科目に分かれ、3年目にその科目に関する卒業論文を作成するという形で、最初から専門分野に特化するのではなく、関連科目の知識も幅広 く習得させることを意図していたようである。なお、正科目の名称は原則として講座名に対応していたが、講座に対応しない科目として史学科の支那史・最近世 史(この2科目は1932(昭和7)年に廃止された)・史学研究法、文学科の文学概論があった。史学研究法と文学概論は専攻科目から除外されていた。ま た、文学科の正科目のうち、英文学・独逸文学・仏蘭西文学・梵語学梵文学については、専攻しない科目の普通講義は1つ選ぶこととされた。
関連諸団体と出版活動
各研究室の整備に伴って、1907(明治40)年2月の教育学研究会発足を皮切りに、正規の授業を補う知的交流の場として各分野の学会・研究会組織が相次 いで設立された。1908年2月には史学科を母体として史学研究会が、1914(大正3)年11月には哲学科を母体として京都哲学会がそれぞれ設立され た。1916年1月には史学研究会が『史林』、同年4月には京都哲学会が『哲学研究』を相次いで創刊し、両誌は今日までわが国を代表する学術誌として刊行 され続けている。こうした分野別の学会とは別に、文科大学全体を基盤にした学会として京都文学会が1910年2月に発足した。これは「哲学史学文学の進歩 及び普及を図るを以て目的と」(同会規則)して、文科大学教授を評議員として組織され、雑誌『藝文』の刊行を主要な事業とするものであった。『藝文』はこ の年の4月に発刊され、月刊誌として市販された。同誌には文科大学の教官や卒業生の研究論文・エッセイのほか、各年度の講義題目・卒業論文題目や学内諸学 会の動向、海外通信等を記載した「彙報」欄もあり、研究紀要と総合雑誌の性格を兼ね備えたものであった。当時他に十分な研究成果発表の媒体がなかったとは いえ、教官数も30名ほどの時代に月刊誌を出し続けているところに創設期の文科大学関係者の並々ならぬ意気込みが感じられる。
この時期にはまた文科大学の出版物として「文科大学叢書」の刊行が始まっている。これは稀覯書の復刻や図書の校勘などによって研究資料を広く学界に供給す る目的で企画されたもので、第1巻は羽田亨による校訂本『大唐西域記』(1911年10月刊)であった。以後、1921年までに6巻が刊行されている。
一方、文科大学創立と同時に教官・学生の親睦を図る目的で学友会が発足した。第1回会合は1906年10月に枳穀邸を会場に教官・学生三十数名が参加して 開かれ、その後毎月のように茶話会・講演会・遠足等の行事を催した。当時は教官・学生ともにごく少人数で、寺子屋のような親密な雰囲気があったことが当時 の教官や学生の回想等から窺われる。
施設の整備
哲学科の授業開始当初は文科大学専用の建物がなく、理工科大学の一部の教室を間借していたが、翌1907年6月に法科大学と共用の2階建木造建築が本部構 内のほぼ中央部(現在の法経本館のすぐ北側)に完成し、その東半分が文科大学に割り当てられて事務室・教官室・教室はこちらに移転した。その東側に翌年6 月に心理学実験室(木造平屋建)が完成、さらにその北側(旧本館と東館にまたがる位置)に1909年5月、2階建の木造建築1棟が竣工し、これが1935 年に撤去されるまで文学部の主要な研究棟となった。研究室は平日は午後4時まで学生にも開放され、教官と学生の交流の場としても機能した。
続いて附属図書館の北側に陳列館が建設された。文科大学に陳列館を附置することは京大創立当初から木下広次総長の構想に含まれており、文科大学設立に先 立って収蔵資料の収集が進められていた。文科大学創設後は三浦周行を初めとする教官による資料収集が本格化し、それら収集品の安全な保管場所の確保が必要 になったことから陳列館建設が1911(明治44)年に決定された。1914年3月に陳列館(煉瓦造二階建)の第1期工事が完了し、同年7月に史学科の全 教室や美学美術史学の研究室がそちらに移転した。同館では研究・教育活動と密着した収集・展示活動を行っており、その収蔵資料には国宝・重要文化財に指定 されているものもある。
澤柳事件
初代文科大学学長の狩野亨吉が在任2年3カ月で退任した後、1908(明治41)年10月に松本文三郎がその後を引き継ぎ、1916年5月まで7年7カ月 (これは歴代最長の任期である)にわたって第2代学長を務め、研究教育体制の確立に尽力した。この時期の重要な出来事として澤柳事件がある。
1913(大正2)年8月、澤柳政太郎総長の決定により計7名の教授が免官となり、その中に文科大学の谷本富教授(教育学・教授法)も含まれていたのであ る。この措置は教授会の自治権の侵害として法科大学の激しい反発を招き、最終的には法科大学側の主張を受け入れた奥田文部大臣の裁定を受けて総長が辞任し (1914年4月)、これを契機として教授会の教官人事権が実質的に確立したとされる。文科大学の教授会は当初、谷本教授の辞職に組織だった抗議をしな かったものの、その後、総長を学内から教官の公選によって選ぶ制度の確立の過程では松本学長を初めとする文科大学の教官たちが指導的役割を果たした(松尾 尊兊『滝川事件』岩波書店、2005)。
2 旧制文学部期(1919~1949年)
学制改革とその影響
1918(大正7)年12月に制定された大学令は帝国大学の他に公立・私立大学や単科大学の設置を認めるものであり、同年の高等学校令とともに両大戦間期 における高等教育の急激な量的拡大をもたらした。これに合わせて1919年2月7日に改正された帝国大学令によって、帝国大学を構成する各分科大学は「学 部」と改称された。同日公布の勅令第13号により京大に置かれる学部が規定され、ここに文科大学は文学部となった。初代文学部長は藤代禎輔である。 1921年には京大を含む各大学の学年歴が変更され、従来9月に始まっていた学年が4月開始になったため、1920年度だけは7カ月で終わることになっ た。また大学令では大学院を各学部に新たに設置される「研究科」を総合したものと規定したが、京大では大学院についての規定にほとんど変化はなかった。
だが学制改革の影響が最も著しく現れたのは1920~30年代における学生数の急増という事態であった。1919年以降の高等学校の増設によって、全国で 8校しかなかった高等学校が大正末年までに34校になり、これに伴って、それまで本科でほぼ30~50名程度、選科で10~30名の水準で安定していた文 学部への入学者数が1922年には本科だけで68名となり、以後増加を続けて1927(昭和2)年には299名を記録した。本科の全学生数でみると 1922年の90名から1929年の709名へとわずか7年間で8倍弱にまで膨れ上がったのである(付録資料参照)。
入学希望者激増への対策として、文学部ではまず1925年12月に学部規定を改正し、翌年より選科生のための学年試験を廃止して修了証書の授与を取り止め た。その結果、選科入学希望者は大幅に減り、選科生徒総数は1925年の139名をピークに減少して以前の水準に戻った。さらに1926年1月に入学定員 を改正し、それまで各学科70名だった定員を哲学科85、史学科40、文学科85と改めるとともに、専攻科目ごとの定員を新たに定めた。この際同時に専攻 科目選定に関する規定を定め、専攻科目の志望者数が定員を超過した場合の学生の振り分け方法等を規定した。ただし、同年3月の教授会では各学科とも志望者 の超過が15名以内の場合は入試を行わないことが申し合わされたうえ、後年にはこの基準はさらに緩和されて、実際にはこれをも上回る志望者を受け入れてい る。
講座と施設の拡充
学制改革以後の大学の拡大は講座と施設の拡充をも伴った。1919(大正8)年6月に国語学国文学と支那語学支那文学に各々第二講座が増設され、次いで 1922年5月に宗教学第二講座(基督教学)、1925年5月に西洋文学第三講座(仏蘭西文学)、1926年6月に宗教学第三講座(仏教学)が開設されて 合計30講座となった。
他方、学生の激増によって施設が狭隘となったため、その増改築が緊急の課題となった。そこでまず哲学科と文学科の研究室用にそれまでの本館に隣接して2階 建の建物が着工され、第1期工事として煉瓦造の西南角の部分が1923年12月に完成すると、ここに両学科の書庫と閲覧室が移された。この建物は5期に分 けて増築され(残りの部分は鉄筋コンクリート造)、1936(昭和11)年10月に完成するが、これが現在の新館完成までの長い期間、文学部中央教室(ま たは本館)と呼ばれたものであり、学部長室や事務室はここに置かれた。また、史学科の拠点である陳列館は1923年12月に第2期工事が竣工、その後も増 築を続けて1929年12月に完成した。
昭和初期の発展
昭和期に入ると講座数の上では学部の拡大は減速し、終戦までの間に新設された講座は1927(昭和2)年10月の哲学哲学史第五講座(西洋哲学史)、 1934年7月の西洋文学第四講座(英文学)、1937年12月の日本精神史講座、1940年12月の伊太利語学伊太利文学講座の計4講座にとどまってい る。このほか、1939年1月の文学部規定改正により西洋古典文学が講座外の正科目として加えられ、専攻学生の受け入れを開始した。
学生数増加に対応して1927年3月に専攻科目選定規定の改正があり、文学科については入学時に志望科目を届け出させ、定員を超過する場合は入試の成績順 に受け入れることとした。前述のように、従来は1回生は学科に分属するのみで2年目に専攻科目を決定していたのだが、文学科だけは入学当初から専攻に分か れる形になったわけである。学科・専攻によって入学志望者には当然ながらばらつきがあり、人気の高い国語学国文学などでは1927年以降、史学科では 1929年以降ほぼ毎年入試を実施せざるをえなかったのに対し、哲学科は定員に満たないことが多かった。こうした趨勢に応じて1933年12月には哲学科 と史学科の入学定員はそれぞれ75名と50名に改められた。
学生数のほうは1933(昭和8)年の756名(選科生を加えると797名)をピークに減り始め、一応の安定期に入ったが、施設の増築は続いた。前述のよ うに本館と陳列館が完成しただけでなく、本館の東隣に東館(鉄筋コンクリート3階建)の建設が始まり、1936年9月に第1期工事が完了した。この過程で 木造の旧本館は取り壊されたが、他方で教室の不足を補うため、1932年10月に陳列館の北に木造平屋?史学科第一教室、次いで1941年5月に東館の東 側に木造2階建の第一教室を建てて対応した。
大正後期から昭和初期にかけては文科大学創設期の教授たちが相次いで停年等により退官する一方、京大出身者が教官に加わっていった時期であった。1936 年10月には小島祐馬が京大出身者としては初めて文学部長に就任している。また1933年4月に文学部卒業生有志による同窓会として「京大倶楽部」(京大 以文会の前身)が結成され、1935年11月には創立30周年祝賀式の開催、『京都帝国大学文学部三十周年史』の刊行といった出来事があり、文学部卒業者 の連帯感も高まってきたようである。ほぼこの頃までには人文学各分野において東大に対抗しうる研究・教育の拠点としての京大文学部の名声が確立され、その 教官や卒業生は哲学科や中国学の諸分野を中心に「京都学派」と呼ばれるようになった。研究活動の具体的内容については各専修の歴史に譲るが、大正~昭和戦 前期の文学部教授から西田幾多郎・狩野直喜・田邊元・羽田亨・新村出・鈴木虎雄の6名の文化勲章受章者が出ていることは特筆に値するであろう。他方、文学 部教官・卒業生による総合雑誌『藝文』は、研究の専門分化が進み、『哲学研究』や『史林』を初めとして各学科・教室を母体とする雑誌の刊行が盛んになるに 従って、当初の意義が薄れてゆき、1931年5月号をもって終刊となった。同時に京都文学会も解散した。
そのほか、1930年3月にはドイツのライプツィヒ大学との間に学生の交換留学の協定が結ばれ、相互に1名ずつ2年間の期限で学生を派遣することが定めら れた。また、1930年代には文学部から小西重直(教育学教授法)・濱田耕作(考古学)・羽田亨(東洋史学)の3名の教授が相次いで京大総長に選出されて おり、学内における文学部の威信の高さを感じさせる。小西は病気のためわずか3カ月で辞任、濱田は就任後1年余りで病没したが、1938年11月に就任し た羽田は1945年11月までの最も苦難に満ちた時代にこの重責を果たした。
戦時体制下の文学部
1937(昭和12)年の日中戦争勃発以降、大学全体に戦時色が強まるなかで、文学部もその影響を免れなかった。「日本精神」振興を意図した前述の日本精 神史講座設置もその現れである(ただしこの講座は例外的に3学科共通とされ、その普通講義が全学生の必修科目とされる一方、専攻科目からは外された)。 1941年8月には防衛団、9月には報国隊が全国の大学と同様に京大でも発足し、大学全体が緊急事態に対応できるように軍隊にならって組織された。 1910(明治43)年以来学友会の恒例行事となっていた修学旅行も1942年を最後に中止となり、その他の学友会の行事も行われなくなった。1941年 には大学在学年限が3カ月短縮されて卒業が12月に繰り上げられ、翌年にはさらに3カ月繰り上げで9月卒業となった。1942年には高等学校の修学年限が 6カ月短縮されたのを受けて京大でも4月と10月の2度新入生を受け入れている。この頃には文学部は再び入学者数が定員割れを起こすようになり、学生の追 加募集を行っていたが、そのため「本来修学の意志なき者が腰掛け的に入学し」、「第二次第三次入学者の過半数は中途退学する」(1942年7月15日教授 会議事録)ありさまであった。
だが戦争の大学への影響が決定的になったのは1943(昭和18)年10月以降である。10月2日公布の勅令第755号「在学徴集延期臨時特例」によって 文系学部および農学部の一部の学生への徴兵延期が停止され、「学徒出陣」が始まったのである。繰り上げ卒業の対象となった1939年4月から1945年4 月までの文学部(本科)入学者のうち、半数弱の638名が徴集されたが、特に1943~44年の入学者に限っていえば、徴集された者の割合は80%前後に も及んだ。また在学中に戦死した文学部生は41名にのぼる(西山伸「京都大学における『学徒出陣』―文学部の場合―」)『京都大学大学文書館だより』第8 号、2005年。卒業後の徴集や戦死の状況は不明)。なお、1943年10月には優秀な若手研究者を確保するため、帝国大学を初めとする特定の大学を対象 に大学院特別研究生制度が発足し、これに採用された大学院生は学資を支給されたうえ召集を免除されて研究に専念できる特権を与えられた。文学部ではこの年 に9名が採用されたが、翌年からは文科系学生は対象外となった。
このように大学から学生が激減したのみならず、残った学生に対しても正常な教育活動は次第に困難になっていった。すでに1939年頃から京大でも始まって いた学生の勤労動員が1944年に入って本格化し、文学部の学生も貯水池の造成や防空壕の建設等の集団作業に動員されるようになった。とりわけ同年5月に 始まった愛知県豊川の海軍工廠への文学部2回生の出動は翌年3月まで続いた。学生は交代で帰学したものの、集中的な勉学はきわめて困難であった。1944 年10月に文学部は「授業並ニ試問ニ関スル臨時措置」を決めて従来の学部規定を臨時に変更し、単位の取得に関する規定を大幅に簡素化して卒業しやすくする ことでかろうじてこの状況に対応した。だが教官たちも、勤労動員への付き添いや食糧不足を補うためのキャンパスの開墾・農作業等に追われて本来の職務を全 うできる状況ではなかった。さらに同年には建物疎開のため心理学実験室や陳列館北側の史学科教室等が撤去された。
文学部の再建
1945(昭和20)年8月15日、日本の敗戦をもって戦争が終わると、復員してきた学生たちが次第に大学に戻り、学内は再び活気を取り戻した。教授会で は急遽授業計画について協議し、年度内は前年に定めた「臨時措置」に従って対応することとなった。復員した学生の回生への割り当ても決められ、授業は10 月11日より開講された。翌年3月には文学部規定を改正し、1945年4月入学者からこれを適用することになった。これによって授業科目は従来の正科目と 副科目の区別に代わって「専攻科目」と「研究科目」に大別され、また全学科にわたって専攻科目を入学時に決めるよう改められた。授業の実態に合わせ、学生 の単位取得の便宜を図っての改正であった。1946年 4月には受験資格を軍関係の学校や専門学校・師範学校等の卒業者にまで大幅に拡大した入試が行われ、文学部には定員の3倍強にあたる714名の受験者が集 まった。この時初めて56名の女子が文学部を受験し、うち12名が合格している。なお、学生の9月卒業は翌1947年まで続き、1948年から1950年 までは3月と9月の2度卒業の機会が与えられた。3月卒業に戻ったのは1951年である。
研究・教育体制の再編と並行して進められたのが連合国最高司令官総指令部(GHQ)の指令に基づく教職員の適格審査である。1945年10月にGHQから 発令された覚書「日本教育制度ニ対スル管理政策ニ関スル件」によって、全国で教員の適格審査を行い、軍国主義者・超国家主義者を罷免するとともに、戦時中 に思想的理由で免職・休職となっていた教員を復帰させることが指示されていた。これを受けて翌年5月に文部省訓令第5号「教職員の適格審査をする委員会に 関する規程」が発令されると、京大でも学部ごとに教職員適格審査委員会が設置された。文学部では落合太郎学部長を委員長とする委員会が6月に発足し、最終 的に西谷啓治教授(宗教学)・鈴木成高助教授(西洋史)・松村克己助教授(基督教学)の3名がその著書・講演等の内容を根拠に思想的理由から不適格と判定 され、1947(昭和22)年から翌年にかけて辞職を余儀なくされた(西谷教授だけは追放指定解除後の1952年2月に同じ講座に復職している)。さら に、西田直二郎(国史)・高山岩男(哲学)両教授と矢野仁一(東洋史)・高瀬武次郎(中国哲学史)両名誉教授の4名は、大日本言論報国会等の指定された団 体に関与していたために、戦争遂行に協力したとみなされて委員会の審査とは別に自動追放該当者として教職追放の指定を受けた。
他方、1946年2月公布の勅令第109号「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」等に基づいて実施された公職追放では、高瀬・矢野両名誉教授と小牧実繁教 授(地理学)の3名が戦時期における指定団体での役職や著作活動を理由に適用を受けた。小牧教授や同じ教室に所属する室賀信夫助教授・野間三郎講師は、追 放を待たずに1945年から翌年にかけて自主的に辞職している。
この時期のその他の出来事としては、1946年3月に京都帝国大学令改正により日本精神史講座が廃止され、翌年7月に哲学・哲学史第六講座(西洋中世哲学 史)が設置されたほか、1948年9月からそれまで教授のみで構成されていた教授会に助教授も出席するようになったこと、同年12月に文学部学友会が新し い会則を制定して学生の自治組織となり、従来文学部長が会長となっていたのを改め学生の中から委員長を選出するようにしたことなどがある。
3 新制文学部期(1949~1996年)
新制大学への移行と教育学部の独立
六・三・三・四制にもとづく新制国立大学は1949(昭和24)年に発足した??、新制京都大学は、旧制第三高等学校を教養課程担当の分 校(1954年に教養部と改称)として併合した上で同年5月31日に発足した。新制文学部の学部規程はこの年の12月19日に制定され、6月1日にさかの ぼって施行された。文学部は後期2年間の専門課程の教育を主として担当することとなり、専門科目は専攻科??と?科目に大別された。また学科への分属と専 攻科目の選択は専門課程への進学時に行われるようになった。新制となって最初の入学試験はこの年の6月に実施され、変則的に入学式は7月、授業開始は9月 であった(したがって新制第1期生は在学3年半で卒業している)。文学部では定員200名に対して479名の志願者があり、226名が入学した。この年と 翌年は旧制・新制両方で学生の募集があったため、文学部の学生数は急増し、1950年度と翌年度には学部学生の総数が1,100名を上回る空前の規模と なった。他方、旧制京大の学生募集は翌1950年で打ち切られ、1954年に旧制最後の卒業式を挙行、その際留年者は新制の学籍に編入されたため、これを もって新制大学への移行が完了した。なお1952年3月には文学部教官の研究成果発表の媒体として『京都大学文学部研究紀要』が発刊され、ほぼ毎年1回発 行されて今日に至っている。
新制大学の発足とともに、文学部の教育学関連の講座を母体として教育学部が新設された。当初は教育学部独自のスタッフがほぼ皆無だったため、文学部長が 1951年3月まで教育学部長を兼任したほか、臼井二尚・矢田部達郎・下程勇吉の3教授がしばらく教育学部教授を併任した。暫定的に文学部に置かれていた 教育学・教授法第二講座(1949年7月設置)および教育心理学講座(1950年5月設置)が1951年4月に教育学部に移管されたのに続き、1953年 8月に文科大学創設以来設置されていた教育学・教授法講座が文学部最後の専攻学生の卒業を待って移管され、翌年3月の旧制文学部の消滅とともに教育学関係 の授業は文学部で行われなくなった。こうして教育学部の独立が完了したが、教育学部の初期の教官には文学部出身者が多く含まれており、その後も両学部間に は現在に至るまで研究・教育上密接な協力関係が続いている。
新制大学院の設置
新制京都大学発足後、新たに設置すべき大学院のあり方について学内で検討が進められてきたが、新制最初の卒業者の出る1953年の1月にようやく設置認可 申請書が文部省に提出され、3月26日に京都大学大学院が設置された。当初は大学院独自の予算や独自のスタッフが全くなく、ゼロからのスタートであった が、旧制大学の大学院が独自のカリキュラムもなく修了者に学位を授与することもない機関で、研究者志望の学生が大学卒業後に籍をおいて教官の指導を受ける 場でしかなかったのに対し、新しい大学院は学生に単位の取得と修了時の論文提出を義務づけるものである。文学部に対応する文学研究科には2年制の修士課程 とこれに続く3年制の博士課程が置かれ、17の専攻(哲学、宗教学、心理学、社会学、美学、国史学、東洋史学、西洋史学、地理学、考古学、国語学国文学、 中国語学中国文学、梵語学梵文学、フランス語学フランス文学、英語学英米文学、ドイツ語学ドイツ文学、言語学)から構成されていた。同年4月7日に研究科 規程が制定され、修士課程では30単位(うち16単位は各専攻の必修科目)、博士課程では20単位(うち12単位は各専攻の必修科目)が修了に必要と定め られた。この年に修士課程に入学したのは67名(うち女子3名)であった。博士課程の学生募集は2年後の1955年から始まり、最初の年には26名(うち 女子2名)が進学した。
学生運動の展開
戦後の京都大学の動きとして重要なものに学生運動の活発化がある。とりわけ1941年に学友会が改組されて成立した同学会は、戦後全学の学生自治組織とし て生まれ変わり、1949年以降執行部内で左派が優勢となってからは大学当局と衝突を繰り返すようになった。1951年11月の天皇事件は特に有名であ り、この時8名の学生に対して無期停学処分が行われたが、そのうち2名は文学部の学生であった。
翌1952年には、4月30日に行われた破壊活動防止法反対等を理由とする文学部学生大会でのストライキ実施決議とその翌日の学内デモ行進に対し、大学は ストライキ禁止を定めた1950年10月の告示第9号に照らしてその責任者として文学部学生3名を停学処分にした。これに抗議する文学部学生大会が6月4 日に開かれ、その決議に基づいて6月5日・17日にストライキが決行されるとともに、先の停学処分撤回と前年の天皇事件で停学となった学生2名の処分解除 を求める要求書が服部総長宛に提出された。しかし、これが受け入れられなかったため、19日から文学部学生3名を含む学生が総長室前でハンガーストライキ を始めた。文学部ではこの日から連日緊急教授会を開いて対応を協議し、学生側とは合意に至らなかったものの、24日に学生大会でハンスト中止が決まった。 この件での処分は破防法反対という動機を考慮して12名譴責という軽いものにとどまった。その後も文学部では翌1953年11月に荒神橋事件、1960年 6月の新安保条約締結反対運動、1962年12月の大学管理法国会上程阻止運動等に際して学生によるストライキが実行された。
高度成長期の文学部
新制大学が最初の卒業生を送り出してから2年後の1955(昭和30)年4月に文学部規程が大幅に改正され、この時に初めて哲学科に11、史学科に5、文 学科に9の「専攻」が置かれることが明記されたほか、「副科目」の名称が廃止されて専門科目は各専攻に属する講義・研究・演習からなると規定された。この 規程はその後、学科・専攻の追加や名称変更、教養課程で履修する科目の名称変更等を除けば、1995年の大講座化までの40年間維持された。また、新制に なった当初は変動のあった学部の入学定員も1957年度からは200名に落ち着き、以後1987年まで変更されなかった。またこの頃までに教官の大半を京 大出身者が占めるようになっていた。1950年代後半から60年代末までの十数年間は新制文学部の体制が確立されて比較的安定した時期といえよう。
規程改正のあった1955年4月には戦時期より活動が中断していた京大倶楽部の再建総会が開かれ、京大以文会と改称された。同会は文学部・文学研究科の同 窓会組織として現在まで会誌『以文』の発行等の活動を続けており、特に大学の法人化以降は文学部をサポートする団体としての役割に期待が高まっている(詳 細は「京大以文会」の項参照)。また翌年11月には文学部創立50周年の記念式典・祝賀会が行われ、京都と大阪での記念講演会、全教官執筆による『五十周 年記念論集』および『京都大学文学部五十年史』の刊行等の記念事業が大々的に執り行われた。
前述のように学生定員は据え置かれたが、新制大学発足から1960年代までの間に、西洋古典語学・西洋古典文学講座(1953年8月)、美学・美術史第二 講座(1956年3月)、西洋文学第五講座(アメリカ文学、1960年4月)、現代史講座(1966年4月)、西南アジア史学講座(1969年5月)の計 5講座が増設された。このうちアメリカ文学の講座は1952年以来文系4学部と人文科学研究所の共同で進められていたアメリカ研究企画を背景として概算要 求をされたものである。またこの時期には心理学(1955年)、考古学(1966年)、地理学(1967年)の3講座が実験講座となった。なお、1964 年には行動科学の発展や心理学・社会学の専門家への社会的需要の高まり等を理由として、心理学・社会学各4講座(文化人類学を含む)からなる「心理・社会 学科」設置案が教授会で審議されている。この新学科設置構想は1967年度から数年間概算要求に盛り込まれたが、教養部から反対意見が出されたこともあっ て結局取り下げられた。
この間、1954年9月の文部省令第23号「国立大学の講座に関する省令」が1964年2月に廃止され、従来設置順につけられていた講座の名称が改められ た。文学部では哲学・哲学史講座が第一講座「哲学」、第二講座「西洋哲学史(古代)」、第三講座「西洋哲学史(中世)」、第四講座「西洋哲学史(近 世)」、第五講座「印度哲学史」、第六講座「中国哲学史」と並べ替えられ(支那哲学史はこの時に中国哲学史に改称)たほか、史学・地理学講座は第一講座が 「西洋史学第一講座」第二講座が「人文地理学講座」、第三講座が「西洋史学第二講座」と改称され、西洋文学講座は第一~第五講座がそれぞれ「ドイツ語学・ ドイツ文学」、「英語学・英文学第一」、「フランス語学・フランス文学」、「英語学・英文学第二」、「アメリカ文学」と改称された。さらに1968年4月 には美学・美術史と現代史の講座名はそれぞれ「美学・美術史学」、「現代史学」と改称された。
前述のような戦後の学生数の増加にもかかわらず、施設の拡充は遅れていたが、戦前に第1期工事が完成したあと未完成のままになっていた東館の増築工事が 1965年3月に竣工し、東館は西側3階に1階継ぎ足し4階建のロの字形の建物になりようやく完成した。考古学を除く史学科各教室は陳列館からこちらに移 転した。この翌年に行われた中央部の噴水を含む東館中庭の造園の費用は京大以文会の寄付によりまかなわれた。次いで1966年3月には鉄筋コンクリート造 2階建の羽田記念館(京都大学文学部附属内陸アジア研究施設)が北区大宮田尻町に完成、翌月に竣工式を行った。これは羽田亨の学問的業績を記念し内陸アジ アの歴史・民族・言語等の研究を振興するため財団法人三島海雲記念財団、武田薬品工業株式会社等の寄付により建設されたものである。同館は2004(平成 16)年4月に学内施設とされユーラシア文化研究センターと改称された(詳細は「ユーラシア文化研究センター」の項参照)。なお、陳列館は1955年に文 部省より博物館相当の指定を受け、1959年に「文学部博物館」と改称された。
大学紛争とその余波
わが国の学生運動は1960年代後半に活発化し、次第に政治問題のみならず各大学の学内問題を直接の契機として展開されるようになっていったが、 1968(昭和43)年から翌年にかけて全国の大学を大学紛争の嵐に巻き込むに至った。そこでは旧来の大学のあり方が学生の立場から問い直され、さまざま な改革要求が大学当局に突きつけられた。京都大学では紛争は1969年1月に学生寮問題を契機として全学に拡大した。1月16日に吉田寮・熊野寮の寮生に よって組織された寮闘争委員会が大学側の対応への不満から学生部の建物を封鎖したのがその発端である。
文学部教授会が1月19日に「緊急事態に対する文学部教授会の見解」を公表して封鎖に反対の意思表示をすると、学友会は教授会の自己批判等を求めて団交を 要求、これが拒否されたため2月3日に無期限ストに突入した。さらに、2月25日から3月1日までの教授会団交を経て、3月11日付けの長尾雅人文学部長 名による「文学部長所信」をめぐる教授会の対応に反発した「L共闘」の学生たちによって3月13日に文学部本館・東館が封鎖される事態に至った。この年に は学部入試が学外での実施を余儀なくされたほか、大学院入試も4月9・10両日に延期のうえ京都市内の予備校で実施された(この際学生の妨害行為があり逮 捕者が出た)。文学部の封鎖は学内の各建物と同様、9月21日に導入された機動隊によって解除されたが、ストライキはなお継続し、11月7日にようやく授 業再開にこぎつけた。12月23日にL共闘大会が開かれ、運動体としてのL共闘が解散を宣言したことをもって文学部の紛争は一段落した。
この間、教授会では2月に文学部改革案検討委員会(第2委員会)を発足させ、文学部改革の理念とその実現の具体案を検討した。2月には専任講師にも教授会 への出席を認めたほか、3月17日には『文学部弘報』を発刊して教授会決定や学部長所信等を掲載した(1973年5月発行の第16号まで不定期刊)。6月 には教官選考に関する内規を改正して選考委員会に教授だけでなく助教授・講師も参加できるようにした。9月には委員会により「文学部改革草案」が作成・公 表された。この際学部長選考内規の改正も検討課題となり、事務職員や学生にも選挙権を認める案も検討されたが、結局教授会での選考という方式が変更される には至らなかった。
京都大学では70年代に入ってからも紛争の余波は長く続き、各学部でしばしば学生によるストライキや団交、授業妨害、建物の占拠・封鎖、施設の破壊といっ た行為が繰り返されたが、特に文学部では学年末試験期間中のストライキが1980年頃まで年中行事のように行われた。1971年4月に学部長との「大衆団 交」の要求が拒否されたのを理由に「L斗」を名乗る学生たちによって学部長室が長期間占拠されたのをはじめ、1973年1月からは経済学部の竹本助手処分 問題をめぐる紛争が全学に波及し、文学部でも無期限ストや学部長室の占拠・建物封鎖があった。また1973年から翌年にかけては、女子学生の卒業論文作成 と大学院進学をめぐる所属教室の教官の対応が当該学生とその支援者から女性差別に当るとして糾弾される事態(「R子さん問題」)が起こった。大学紛争の 間、教授会は学生の妨害を避けるためしばしば学外で転々と会場を移して開催されたほか、2期2年間務めるのが通例になっていた学部長職は1969年から 81年までの間、藤澤令夫(在任1974年1月~76年1月)を除き1年で交代している。
教育・研究体制の再編
1970年代から80年代にかけては、大学紛争中に必要性の指摘されていた大学院の改革・拡充が京都大学全体で推進されたが、文学部でもこれに関連した動 きがあった。まず1975(昭和50)年10月に京都大学通則の一部改正に合わせて大学院文学研究科規程を改正し、これによって5年間の課程全体が修士課 程と博士後期課程からなる「博士課程」となり、博士後期課程では単位取得の要件が廃止された。またこの年には大学院教育の充実を図るため、翌年度の概算要 求に既存の複数の講座と協力関係に立つ3つの大学院講座(比較社会学・比較考古学・比較文学)の新設が盛り込まれた(この際、附置研究所等との協力関係の 緊密化、専攻の再編成など、90年代に実現する改革構想も同時に打ち出されている)。このうち比較社会学講座だけが翌年5月に文学部としては初めての大学 院講座として(助手以外に専任教官ポストのつかない客員講座ではあったが)設置された。これ以外にも大学院講座の設置要求はその後引き続き行われたが、大 学院講座という形ではいずれも実現しなかった(ただし、いくつかは文化行動学科設置および大講座化の際に博士講座として設置された)。このほかに心理学第 二講座(1973年4月)、フランス語学・フランス文学第二講座(1980年3月)、社会人間学講座(1986年3月)、地域環境学講座(1989年5 月)が増設された。このうち4講座は後に文化行動学科に所属することになる。なお、1975年に社会学と美学・美術史学第一・第二、1976年に言語学の 各講座の実験講座化が相次いで実現した。
施設に関しては、陳列館の老朽化が著しくなったため、西・北部分を解体してその跡に鉄筋コンクリート4階建の文学部博物館新館が建設され、1986(昭和 61)年7月に竣工した。同館は東大路通に面した入り口をもち、翌年11月から春秋2回の一般公開と公開講座を始めたが、財政的理由で文学部の附属施設と しての運営が次第に困難になったため、1997(平成9) 年4月に京都大学総合博物館に移管された。
この時期にはまた国公立大学の入試制度改革があり、文学部としてもそれへの対応を迫られた。1987年には1979年の共通第一次学力試験(共通一次試 験)導入により1回になった国公立大学の受験機会を複数化するため、国公立大学の入学試験がA・B両日程に分けて実施された。文学部では入学辞退者の増加 を見込んで入学定員220名(この年から従来より20名増員された)に対して350名を合格させたが、それでも140名という大量の辞退者(大半は東京大 学の合格者)を出し、やむなく10名の追加合格者を出すという事態が起こった。文学部はこれを「本学部の学風に志を寄せる個性あるすぐれた学生を選抜する という本学部の入試方針とかけはなれたきわめて不本意な結果」と評価し、翌年度の入試については抜本的改革を西島総長に要望した。翌1988年度の入試で は文学部は他の文系学部と同様、大半の定員をB日程に割り当てた結果、追加合格者は出さずにすんだ。なお学部学生の入学定員は1991(平成3)年度から 3年間240名に増員されたが、1994年に220名に戻って現在に至っている。
京都大学ではかねてから教養部を改革する構想があり、一時は教養部所属の教官を各学部に移籍させる案も検討されたが、文学部では、各専攻の規模からみて影 響が大きいこと、多数の語学担当教官の移籍には問題が多いことなどを理由にこれには消極的な姿勢をとった。結局大学設置基準の大綱化のもとで教養部は 1993(平成5)年に総合人間学部に改組されることになり、それに先立って1992年4月からは一般教育科目に代わって全学共通科目が開講されたが、こ れに伴って文学部もカリキュラムの見直しを迫られた。その際、専攻への分属の時期を早めることも検討されたが、結局当面現行通り3回生分属を続けることに なり、その代わり授業の一部を1・2回生に下ろすこととなった。1992年12月に文学部規程を改正して、授業科目を「学部科目」と「全学共通科目」から なると改めたほか、科目等履修生および特別聴講学生の入学を認めた。
文化行動学科の新設
創立以来続いてきた哲・史・文3学科体制に4つ目の学科を加えることについては、前述のように60年代から心理・社会学科新設計画として構想されてきた が、その後心理学・社会学・地理学教室の関係者の間で「カリキュラム、設備等の点での協力関係を緊密にし、相互に連関する研究領域を開拓するための体制を 整えることを目的として」(1984年3月19日教授会議事録)第4学科の設置に向けた協議が進められるようになった。1984(昭和59)年4月には新 学科の名称を「文化行動学科」とし、上記3教室の既存の講座に若干の新設講座を加えた形でその設置を翌年度の概算要求事項とすることが決まった。文化行動 学科は1992(平成4)年に設置され、哲学科から基礎心理学(旧心理学第一講座)、実験心理学(旧心理学第二講座)、社会学、社会人間学、比較社会学の 5講座、史学科から地理学、地域環境学の2講座が移行したうえ、言語科学、科学哲学・科学史の2講座が新設されて合計9講座で発足した。同年4月には文学 部規程が一部改正されて学科編成に文化行動学科が加えられ、心理学、言語科学、社会学、地理学(人文地理学から改称)、科学哲学科学史の5専攻が置かれた (専攻の名称には、正式な講座名に含まれるナカグロ[・]が省かれるのが通例となっている)。なお、翌年5月には再度文学部規程の一部改正があり、各学科 に学科長が置かれた。
4 大学院重点化以降(1996年~)
『21世紀の文学部像』
1992(平成4)年5月、文学部に文学部再編計画委員会が設置され、文学部における人事運用の柔軟性を高め、また財政危機を脱することを主たる目標とし て、文学部の教育研究体制の大規模な再編が始まった。その方向性を最初に示したものが1993年4月に出された『21世紀の文学部像―教育研究体制を中心 に―』であり、これを踏まえ現状を把握しようとしたのが1995年3月に刊行された『京都大学文学部の現状と課題 自己点検・評価報告書』である。
『21世紀の文学部像』は、全58頁と大部なものでないが、文学部の自己点検自己評価報告書の先駆をなすものであり、大講座化、大学院重点化を前に現状を 総括したものである。本報告書は、学部長、評議員、各学科代表、各学科から1名の委員で構成された「21世紀文学部像」研究会の名で公にされたもので、は じめに、I 学部・大学院の現状、II 学部・一般教育のあり方、III 大学院教育・研究のあり方(一)-人文科学の充実と発展-博士号取得のための教育体制-、IV 大学院教育・研究のあり方(二)-人文科学の国際化-、V 新しい学術ネットワークのあり方、VI 自己点検・評価、おわりに、で構成されている。いまここにその全てを紹介することはできないが、VIの自己点検・評価から少し紹介する。この章は、1)自 己点検・評価の基本理念と目的、2)自己点検・評価の基準、3)自己点検・評価についての留意点とからなり、1)では以下のように述べている。
大学の自己認識としての自己点検・評価は、究極的には大学の研究と教育の基礎にある学問の理念に発する、大学自身の営みである。大学が人類文化における学 問の主要な担い手として研究と教育の役割を果たしているか否かが、ここでは根本問題となる。特に人文科学の担い手としての文学部の役割は極めて大きいか ら、本文学部の自己点検・評価には一研究教育機関内の個別的点検・評価で終わることが許されない普遍的・世界的な視野と水準が要求されることになろう。し たがってまた自己点検・評価の目的も、このような理念に照らして文学部の現状を徹底的・批判的に認識し、それによって現状を改革して理念にふさわしい姿に 出来る限り近づけることに認められなければならない。
そして、2)で、基準は、「国際的な大学の研究と教育の水準に即したものでなければならない」とし、また「この基準は理念的・包括的な性格をもつもので あって、点検・評価の具体的項目をそのことから直ちに演繹することはできない」と述べ、3)では、「点検・評価は、学部、学科、専攻、個人等の各レベルで 連携してなされてはじめて効果を発揮する」とし、また「点検・評価には、中・長期的視点が不可欠である」こと、「他者による評価を排除する自己評価は、自 己正当化と独善に堕する」とし、さらに「自己点検・評価がなされた場合に重要なことは、学部の将来像、将来計画、理念に照らしてそこから見いだせる問題点 を明確に指摘することである」と記している。現状においても傾聴すべき内容ではなかろうか。
なお、1995年6月に『21世紀の文学研究科(大学院)-大学院再編と新たな教育研究体制-』が、大学院重点化を目前に作成されている。
『京都大学文学部の現状と課題 自己点検・評価報告書』
1995(平成7)年3月に出された『京都大学文学部の現状と課題 自己点検・評価報告書』は、文学部の本格的な自己点検・評価報告書としては最初のもの である。全324頁の大部なものである。本報告書は、第1章 教育研究の理念と目標、第2章 文学部の教育活動、第3章 文学部の研究活動、第4章 附属施設の活動、第5章 図書と学術情報、第6章 社会との連携、第7章 専攻の研究・教育活動、第8章 教官の研究・教育活動、第9章 自己点検・評価実施の経緯、の9章でなっている。第9章 自己点検・評価実施の経緯によりながら、文学部自己点検・評価の経緯を辿ることにする。
文学部では、1992年1月の教授会で、自己評価等の検討を連絡委員会で取り扱うことが了承され、同年3月、点検項目等の検討を行うために「自己評価等検 討小委員会」が設置された。小委員会は同年4月「文学部の自己点検・評価項目案」を作成した。そこには、評価項目として、文学部の教育研究の目標理念、教 育活動、厚生補導、研究活動、国際交流、図書と学術情報、社会との連携、教員組織、施設・設備、財政、管理運営、個人調書、の12項目があげられたうえ で、自己点検・評価のあり方について小委員会の意見と要望が付せられている。
次いで1993年2月23日「京都大学自己点検・評価実施規定」が施行されたのを受けて、同年4月に「文学部自己点検・評価委員会」が設置され、当委員会 において『京都大学自己点検・評価報告書』の文学部担当分の作成がなされた。同報告書は、1994年6月に公刊された。
文学部自己点検・評価委員会は、1994年4月より学部としての報告書の作成に着手した。基本方針として、1. 本学部としては最初の点検作業であることを考慮して、現状の調査・検討から始めてほぼ過去10年位の基礎的なデータを集積することにより、報告書に白書的 な性格を持たせること、2. 具体的な評価事項については小委員会が作成した上述の項目案に依拠すること、3. 点検・評価は学部・専攻・個々の教官の各レベルで連携して行うよう努めることが、教授会で了承された。この時の点検・評価は、教育と研究の内容に直接関わ る項目に限定され、教員組織、管理運営、施設・設備、財政等は、この時期、学部・大学院の改組・再編計画と建物の改築が進行中であることから、明年以降に 送られた。
本報告書の編者が「当初の方針からすると、専攻と教官ごとの点検・評価が詳細にわたっているのに比べて、学部全体としての点検・評価が十分でないことも否 めないところである」と記しているように、『21世紀の文学部像』が示した評価の方向性等は必ずしも十分に生かし切れていない。
1995年の大講座化
大講座化は、1993年11月に文学部再編計画案として教授会で承認され、概算要求がなされた。1994年6月、文部省のヒアリングを受け、翌1995年 1月の内示で大講座化が認められた。その結果、1995年4月より、従来哲学科・史学科・文学科・文化行動学科の4学科44講座であったものが人文学科1 学科16大講座(実験講座10、非実験講座6)へと改編された。この結果、従来教授45名、助教授46名、講師1名、助手11名であったものが、助教授6 名と助手9名が教授に振り返られ、教授59名、助教授40名、講師1名、助手2名となった。
16大講座は、国語学・国文学講座(教授2名、助教授2名)、中国語学・中国学講座(教授2名、助教授2名)、東洋古典学講座(教授4名、助教授4名)、 西洋古典学講座(教授2名、助教授1名)、ヨーロッパ・アメリカ語学・ヨーロッパ・アメリカ文学講座(教授8名、助教授7名)、哲学・宗教学講座(教授8 名、助教授7名)、美学・美術史講座(教授3名、助教授2名、助手1名)、日本史学講座(教授3名、助教授2名)、東洋史学講座(教授5名、助教授3名、 講師1名)、西洋史学講座(教授3名、助教授1名)、考古学講座(教授2名、助教授1名)、心理学講座(教授3名、助教授2名)、言語学講座(教授3名、 助教授1名)、社会学講座(教授3名、助教授1名、助手1名)、地理学講座(教授3名、助教授1名)、現代文化学講座(教授5名、助教授2名)である。な お、このとき日本史学(国史学を改称)、東洋史学、西洋史学、現代文化学、地理学のうち地域環境学講座が新たに実験講座化した。
こうした大講座制のもとで、教育研究組織を現実的に運用するために、東洋文献文化学系、西洋文献文化学系、思想文化学系、歴史文化学系、行動文化学系、現 代文化学系の6系が置かれ、東洋文献文化学系には、国語学国文学、中国語学中国文学、中国哲学史、サンスクリット語学サンスクリット文学、インド哲学史、 仏教学の6専修が、西洋文献文化学系には、西洋古典学、スラブ語学スラブ文学、ドイツ語学ドイツ文学、アメリカ文学、フランス語学フランス文学、イタリア 語学イタリア文学の7専修が、思想文化学系には、哲学、西洋哲学史、日本哲学史、倫理学、宗教学、キリスト教学、美学美術史学の7専修が、歴史文化学系に は、日本史学、東洋史学、西南アジア史学、西洋史学、考古学の5専修が、行動文化学系には、心理学、言語学、社会学、地理学の4専修が、現代文化学系に は、科学哲学科学史、情報・史料学、二十世紀学、現代史学・現代日本論の4専修が設けられた。
なお、この大講座化の段階では、大学院の教育研究組織は従来のままである。
大学院重点化と人文科学研究所
大講座化を踏まえ引き続き大学院重点化が文学部でも推進されるが、この過程で表面化したのが人文科学研究所との関係である。
1962(昭和37)年から「自然科学系の大学院拡充の必要性」を掲げ附置研究所教官の大学院に対する協力体制の整備が文部省によって始められたが、この 動向に対し文学部教授会は、大学自治の観点から憂慮を示し、平沢総長に意見書を提出した(コラム参照)。にもかかわらず、1968年には、文学研究科にも 附置研究所による大学院拡充がはかられた。具体的には、人文科学研究所の講座に博士・修士の定員を付け、それを文学研究科の各講座に貼り付けるものであっ た。しかし京都大学事務当局は、先の文学部からの意見書に鑑み、このことを文学部に通知しなかった。その後も、人文科学研究所に新しい講座が新設されたと きには、文部省からそれに対応する大学院定員が増員されたが、それもまた文学部に伝えられることはなかった。
こうした取り扱いが、大学院重点化を進めるなかで解決すべき問題として浮上し、1993(平成5)年10月に文学部は人文科学研究所に協力要請をし、12 月には人文科学研究所はその要請を受け入れた。
その後、人文科学研究所の教員の大学院文学研究科協力講座への参加者、大学院生との関係、教授会運営等について両者で話し合いが繰り返され、最終的には 1996年5月に「文学研究科協力講座の発足にあたっての文学研究科長・人文科学研究所長の基礎的取り決め」が両者によって調印された。結果、人文科学研 究所からは17名の教官が協力講座として参加することになり、文学研究科の学生定員は、最終的に修士126名、博士63名となった。
コラム 人文研の大学院定員
1962(昭和37)年2月7日、「自然科学系の大学院拡充の必要性」と「附置研究所の要望」とを踏まえ、附置研究所教官の大学院に対する協力体制の整備 が文部省より一方的に求められた。京都大学では、同月14日に各部局にこの通達が示されるが、こうした動きに対し文学部教授会は、大学自治の観点から慎重 な態度でのぞむよう以下のような要望書を平沢興総長に提出した。
昭和三七年二月二〇日 京都大学 文学部教授会 京都大学総長 平沢 興 殿 こうした文学部の要望にもかかわらず、京都大学は、この年、理学・医学・工学・農学研究科で修士47名、博士5名の増員を文部省に申請し、翌年、申請どお り認められた。当初、自然科学系の大学院拡充をめざすものであったが、大学院拡充の方針はその後も継続して進められ、1968年には文学研究科についても 適用され、人文科学研究所分として修士13名博士12名の増員がなされた。その詳細は別表のとおりである。その後、1970年に哲学博士1名(人文・西洋 思想)、1973年に国史学修士1名(人文・日本文化)、1975年に国史学博士1名(人文・日本文化)、1979年東洋史学修士1名(人文・現代中国) 等の増員がなされた。1994年時点での定員は、修士15名、博士15名であった。 別表 1968年次の人文研協力講座
|
大学院重点化
1996(平成8)年4月、前年の大講座化を踏まえ大学院重点化がなされた。これは、従来の学部を主とし大学院をその上に置くあり方を変え、大学院を主と しそのもとに学部を置くものである。1996年度の概算要求がなされ、1995年2月の文部省ヒアリングを経て、1996年1月に文部省から大学院重点化 認可の内示を受けた。
大学院重点化の教育研究組織は、前年の大講座制の枠組みを基本的には継承(ヨーロッパ・アメリカ語学・ヨーロッパ・アメリカ文学講座が欧米語学・欧米文学 講座と改称)しつつ、新たに大講座の上位の組織として、文献文化学専攻(国語学・国文学講座、中国語学・中国学講座、東洋古典学講座、西洋古典学講座、欧 米語学・欧米文学講座)、思想文化学専攻(哲学・宗教学講座、美学・美術史講座)、歴史文化学専攻(日本史学講座、東洋史学講座、西洋史学講座、考古学講 座)、行動文化学専攻(心理学講座、言語学講座、社会学講座、地理学講座)、現代文化学専攻(現代文化学講座)の5専攻が設置され、加えて専攻共通のもの として総合文化学講座、協力講座として文献文化学専攻には文献文化論講座、思想文化学専攻には思想文化論講座、歴史文化学専攻には歴史文化論講座、現代文 化論専攻には現代文化論講座が置かれた。総合文化学講座(客員講座)には、従来2名であった国内客員講座が増員され3名に、また2名の外国人客員講座が設 けられた。
この重点化にあたり実際の教育研究運営は、専攻を大講座化の際に採られた系に読み替え、かつ文献文化学専攻を東洋文献文化学系と西洋文献文化学系に二分 し、計6系とし、そのもとに専修を附属させたが、学部組織である英語学英文学専修とアメリカ文学専修とは、従来どおり大学院では英語学英米文学専修とされ た。また、2004年度よりサンスクリット語学サンスクリット文学とインド哲学史とが合体しインド古典学となり、現状では専修数は31である。またこの 年、現代史学・現代日本論が名称を変更し現代史学となった。
この大学院重点化に際し、学部の系の名称が変更され、思想文化学系は哲学基礎文化学系、東洋文献文化学系は東洋文化学系、西洋文献文化学系は西洋文化学 系、歴史文化学系は歴史基礎文化学系、行動文化学系は行動・環境文化学系、現代文化学系は基礎現代文化学系に改称した。
教員人事の柔軟化とともに大学院重点化のもう一つの目標であった文学部・文学研究科の財政問題は、大講座化の前年、1994年の決算額が、 247,663,000円であったのに対し、重点化の初年度1996年の決算額は、401,259,000円(建物新営等設備費67,291,000円を 除く)となり、危機的状況から脱出した。2005年の決算額は394,037,000円であり、それほど大きな減少ではないが、今後、効率化係数等が適用 され、このままでは財政は徐々に縮小していく。
重点化以降の大学院入学者の動向
大学院重点化以前の文学研究科の1学年の定員は、文学部側の理解では修士79名、博士40名であったが、先に述べたように、1968(昭和43)年以降の 人文科学研究所に付けられた修士15名、博士15名の定員があった。これらが大学院重点化に際し変更され、修士126名、博士63名となり、修士・博士と も増加したが、修士定員の増加は相当大きなものであった。
1996(平成8)年以降2005年度までの修士および博士の専修別入学者数は表2・表3のとおりである。修士入学者は、いずれの年も定員に満つることは なかったが、100名を割ることもなく、最高119名、最低101名、平均108.8名である。
一方、博士課程については、最高81名、最低54名であるが、平均は67.3名と定員を超えている。しかし、2002年以降減少し、特に2004年以降は 定員を割っている。
表2 修士課程入学者数(1996年度以降)
| 専修 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 合計 |
| 国語学国文学 | 7 | 9 | 12 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 83 |
| 中国語学中国文学 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 42 |
| 中国哲学史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| サンスクリット語学サンスクリット文学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 7 |
| インド哲学史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| インド古典学 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 仏教学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 西洋古典学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| スラブ語学スラブ文学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ドイツ語学ドイツ文学 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25 |
| 英語学英米文学 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 55 |
| フランス語学フランス文学 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 45 |
| イタリア語学イタリア文学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 哲学 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 43 |
| 西洋哲学史 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 48 |
| 日本哲学史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 倫理学 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 宗教学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| キリスト教学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 美学美術史学 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 50 |
| 日本史学 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 65 |
| 東洋史学 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 80 |
| 西南アジア史学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 西洋史学 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 54 |
| 考古学 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 |
| 心理学 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 |
| 言語学 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 46 |
| 社会学 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 72 |
| 地理学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 科学哲学科学史 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 21 |
| 情報・史料学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 二十世紀学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| 現代史学・現代日本論 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 22 |
| 現代史学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 |
| 計 | 111 | 115 | 108 | 119 | 101 | 106 | 107 | 104 | 109 | 108 | 1088 |
表3 博士後期課程進学・編入学者数(1996年度以降)
| 専修 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 合計 |
| 国語学国文学 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 44 |
| 中国語学中国文学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 27 |
| 中国哲学史 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| サンスクリット語学サンスクリット文学 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| インド哲学史 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
| インド古典学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 仏教学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 西洋古典学 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| スラブ語学スラブ文学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| ドイツ語学ドイツ文学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 英語学英米文学 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| フランス語学フランス文学 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 31 |
| イタリア語学イタリア文学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 哲学 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 西洋哲学史 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 日本哲学史 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 倫理学 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 宗教学 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| キリスト教学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 美学美術史学 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 |
| 日本史学 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 45 |
| 東洋史学 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35 |
| 西南アジア史学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 西洋史学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 33 |
| 考古学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| 心理学 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 36 |
| 言語学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 社会学 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 57 |
| 地理学 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 |
| 科学哲学科学史 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 情報史料学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 二十世紀学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 現代史学・現代日本論 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 15 |
| 現代史学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 66 | 61 | 81 | 78 | 69 | 80 | 62 | 66 | 56 | 54 | 673 |
文学部新館の完成
1993(平成5)年3月、京都大学の中核的施設が集まり高密度が主な原因となって引き起こされている学園環境の劣化を解消するために、全学において吉田 キャンパス施設長期計画が策定された。そこでは吉田キャンパスを西南から東北へと「幹線緑道」の設置が構想され、その結果、その線上に位置する文学部東館 の取り壊しとその跡地の緑地化が計画された。それと同時に、整備計画が策定された。
それによると時計台は残し、その北にほぼ対象形に片側4棟、計8棟の建物が建てられることになっていた。1993年度、最初に着手されたのが文系四学部共 同棟であり、1994年度に文学部講義棟が、1995、1996年度をかけて文学部新館が建てられる計画であった。以降法経東北館、法経東南館、法経西南 棟、法経西北棟、教育学部新棟と建設されることになっていたが、既存建物の使用期限延長を骨子とするいわゆる「有馬レポート」が出されたのを受けて、 1997年6月の全学の建築委員会において計画が変更され、法学部本館は耐震工事を施したうえで利用することとなり、当初の計画は大きく変更された。
文系四学部共同棟は、実際には1993年12月に着工し、竣工したのは1994年12月である。この共同棟には、文学部新棟建築のために文学部旧本館西側 が取り壊されたために、主として取り壊された研究室と文学科閲覧室が入った。またこのとき哲学科閲覧室が美学美術史の研究室へ一時移転した。
文学部新館第一期工事(講義棟)は、1995年7月にはじまり翌1996年3月に竣工した。この建物は主として講義棟であるが、地下には閲覧室および書庫 が設けられ、同年8月、哲学科閲覧室が移るとともに、文学科閲覧室と統合した。文学部新館第二期は、1997年3月から工事が始まり、8月に完成、その直 後、東館にあった史学科閲覧室が完成した新館に移り、従来3閲覧室であったものが1閲覧室に統合された。
この間、教官研究室は、大講座化以降の教官の増員も重なり、不足を極め、東館4階の会議室や文学部博物館の名誉教授室を教官研究室として分割配分し、また 教授会の場も文学部博物館講演室をもってあてられた。
いっぽう文学部東館は、1993年の吉田キャンパス建築計画によって、文系建物群が完成する予定の2003年度までには取り壊されることになっていたが、 1997年の法学部本館の改築から修築への計画変更、2002年から始まった工学部の桂移転にともなう吉田キャンパス再配置計画の策定により、1993年 当初の計画は大きな変更を迫られた。2000年6月6日、全学建築委員会で見直しが行われ、工学部4号館および工学部9号館の文系学部での改修利用が決定 され、2002年3月19日の全学建築委員会で、文系四学部共同棟2200㎡と工学部4号館1800㎡とを文学部が使用することになり、それへの移転が修 了した段階で東館は取り壊すことになった。当初、これらの計画は、2003年度に完了する予定であったが、実際には耐震工事の遅れなどもあって、いまだに 実現していない。
文学研究科主催のシンポジウム
大学院重点化のなった1996(平成8)年から文学研究科では、研究科内の研究状況を相互に理解し、また一般市民にも広く文学研究科の研究活動の一端を紹 介できればとの思いからシンポジウムを企画した。以下、各年の開催日時とテーマを列記しておく。なお、第6回以降は、文学部同窓会京大以文会の後援をえ、 第7回以降は「京都大学文学研究科国際シンポジウム」と称するようになり、また第8回、第9回は、21世紀COEプログラム「グローバル化時代の多元的人 文学の拠点形成」(代表:紀平英作)の研究成果の一部の公表を兼ねて開催され、同プログラムとの共催である。第10回は、21世紀COEプログラム「グ ローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」との共催であるとともに、2005年4月の北京大学歴史学部との学術交流協定締結を記念して開催されたものであ る。
- 第1回 1996年11月30日 創立期の京大文科 -東洋学の群像-、西欧における表象文化-文学と芸術のあいだ-
- 第2回 1997年11月29日 人文的教養のゆくえ
- 第3回 1998年11月28日 高度情報化時代の人文学
- 第4回 1999年11月27日 病い-その思想と文化-
- 第5回 2000年12月9日 古代人のメソドロジー、-人間性の原点を探る二一世紀の歴史学-
- 第6回 2001年12月1日 日本文化の基点-中世から近世へ-
- 第7回 2002年11月30日、2002年12月2日 歴史の現在を問う、「自然という文化」の射程
- 第8回 2003年12月6日 文学と言語にみる異文化意識
- 第9回 2004年12月4日 空間の行動文化学
- 第10回 2005年12月17日 京都と北京:光の交わるところ-学問知から人類知へ
ティーチング・アシスタントとリサーチ・アシスタント
ティーチング・アシスタント(TA)は、1992(平成4)年に「優秀な大学院生に対し、教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ、これに対する手当支給に より、大学院生の処遇の改善に資するとともに大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図ることを目的」として創設された制度である。
他方、リサーチ・アシスタント(RA)は、1996年度より導入された制度で、その目的は、「対象機関における学術研究の一層の推進に資する研究支援体制 の充実・強化並びに若手研究者の養成・確保を促進するため、当該対象機関が行う研究プロジェクト等に、優れた大学院後期博士課程在学者を研究補助者として 参画させ、研究活動の効果的推進、研究体制の充実及び若手研究者としての研究遂行能力の育成を図ること」にある。
文学部・文学研究科における現在までのTAとRAの採用の推移は以下のごとくである。
表4 TA・RAの推移 単位:名
| 年度 | TA | RA |
| 1992 | 38 | – |
| 1993 | 37 | – |
| 1994 | 51 | – |
| 1995 | 38 | – |
| 1996 | 53 | 1 |
| 1997 | 84 | 6 |
| 1998 | 91 | 7 |
| 1999 | 97 | 9 |
| 2000 | 97 | 14 |
| 2001 | 137 | 14 |
| 2002 | 44 | 15 |
| 2003 | 34 | 13 |
| 2004 | 34 | 13 |
| 2005 | 35 | 12 |
奈良女子大学大学院人間文化研究科との学生交流
1999(平成11)年11月1日に、京都大学文学研究科と奈良女子大学大学院人間文化研究科との間で学生交流協定が締結された。内容は、2000年4月 1日から施行、修士課程学生(奈良女子大学では博士前期課程学生)を対象とし、両研究科相互に授業を提供、単位を認定するものであった。受け入れた学生の 身分は特別聴講学生とし、それに付随する授業料は非徴収である。特別聴講学生が履修できる授業科目及び単位数は、それぞれ5科目、10単位とされた。現在 までの交流の状況は、以下の通りである。
表5 交流学生の変遷 単位:名
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 京都大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 奈良女子大学 | 6 | 5 | 11 | 15 | 14 | 14 |
教員の特別研究期間
2000年3月22日の教授会において、「特別研究期間についての申し合わせ」が承認された。これは、「文学部・文学研究科は、教官の責務である研究・教 育・大学運営のうち、研究活動がその性質上高度の時間的集中を必要とするものであることに鑑み、特別研究期間を設定」したものである。
内容は、在職期間5年について1回、特別研究期間を年度の前期または後期の6カ月、あるいは在職期間10年について1回、1年とし、期間中の研究テーマ は、「研究者固有の研究テーマのほか、教育活動の充実や大学運営の改善を直接の目的とするもの」も対象とした。
この制度は、2000年4月から施行されたが、現在この制度を利用した教官・教員は、2名に止まっている。
学術交流協定の締結
1984(昭和59)年12月24日に、文学部は、教育学部・法学部・経済学部・人文科学研究所とともにハーヴァード大学燕京研究所(アメリカ合衆国) と、教員又は研究者の交流、学生の交流、共同研究の実施を内容とする学術交流協定を締結した。文学部としては最初の国際交流協定である。
1994(平成6)年5月30日に、文学部とローザンヌ大学文学部(スイス)とのあいだで、教員及び研究者の交流、学生の交流、学術図書及び出版物の交 換、共同研究及びシンポジウムの実施を内容とする学術協定を締結した。この協定は、1997年6月30日に京都大学とローザンヌ大学のあいだで大学間交流 協定が締結されたために解消した。なおこの学術協定は、本学部独自のものとしては最初のものである。
ついで、1998年3月27日に、ジュネーヴ大学文学部(スイス)との間で、学生の交流、教員・研究者の交流、学術情報の交換、シンポジウム・セミナー・ 講演会の共同開催、共同研究計画の推進を内容とする学術交流協定、1999年7月16日に、ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院(連合王国)との間で、学 術資料・刊行物及び情報交換、教員又は研究者の交流、学生の交流、共同研究及び研究集会の実施を内容とする学術交流協定、2003年11月11日に、パリ 第8大学「歴史、文学、社会学」学部(フランス)との間で、学生の相互交流、教員・研究者の相互交流、出版物・学術情報の交換、シンポジウム・セミナー・ 講演会の共同開催、共同研究計画の推進を内容とする学術交流協定、2005年4月13日に、北京大学歴史学部(中国)との間で、学術研究者及び学生の交 流、学術情報・書籍・論文の交換、学術上及び教育上有益と思われる共同事業の実施を内容とする学術交流協定、2005年7月1日に、ロシア科学アカデミー 東方学研究所サンクトペテルブルグ支所(ロシア)との間で、学術研究者及び学生の交流、学術情報・書籍・論文の交換、学術上及び教育上有益と思われる共同 事業の実施を内容とする学術交流協定を締結した。
この結果、現在、文学部・文学研究科では、6か国6大学とのあいだで学術交流を推進している。
キャンパス・ハラスメント
1995(平成7)年、文学部・文学研究科に、性差別にかかわる人権問題の相談窓口が開設された。しかし、当初、この相談窓口開設が学生に周知されていな かったことに鑑み、1998年度の学生便覧に「性差別にかかわる人権問題の相談窓口の存在について」が、1999年度の学生便覧に「性差別の防止のための ガイドライン」と「「性差別等相談窓口」について」が、さらに2000年度の学生便覧に加えて「カウンセリングセンター」の紹介が、掲載された。
2000年6月、セクシュアル・ハラスメントに関する問題を扱う全学の人権問題対策委員会が設置され、またセクシュアル・ハラスメント相談窓口への訴えを 機に、同年10月文学部・文学研究科に人権問題対策委員会が設置された。
前年10月に窓口へ訴えられた文学研究科教授のセクシュアル・ハラスメント疑惑に関する調査を行うため、2001年1月11日に「文学部・文学研究科人権 問題調査委員会」が設置された。その後、「調査委員会」による調査が重ねられ、教授会での検討を経たあと、2001年6月19日の評議会で懲戒処分が決定 された。これを受けて、6月21日で文学研究科は、以下のような告示を出した。
去る六月十九日の京都大学評議会において、文学研究科教授のセクシュア・ハラスメントの件で懲戒処分が決定された。
文学研究科・文学部では、この件が昨年十月にセクシュアル・ハラスメント相談窓口に訴えられて以来、事態を深刻に受けとめ、教授会のもとに「人権問題対策 委員会」、さらに「調査委員会」を設置して、事実究明のために最大限の調査を行い、教授会で検討を重ねた。同日の評議会での懲戒処分は、以上の結果に基づ くものである。
厳正であるべき教育・研究の場でこのような事態が生じたことは誠に遺憾である。文学研究科・文学部としては、こうしたセクシュアル・ハラスメントを今後二 度と起こすことなく、学生諸君が安心して勉学に専念できる環境を確立するために努力する所存である。
平成十三年六月二十一日
文学研究科
こうした状況を踏まえ、2001年9月に相談窓口についてより詳細に紹介するパンフレット「「セクシュアル・ハラスメント等相談窓口」について」が作成さ れ、窓口で配布され、翌年の学生便覧に載せられた。さらに2004年10月には「キャンパス・ハラスメント・ガイドライン」が新たに定められ、キャンパ ス・ハラスメントの一層の防止をめざす努力がなされている。
京都大学文学研究科フォーラム「京都から世界へ-知の次なる一歩」
2002(平成14)年6月15日、京都会館第二ホールにおいて、京都大学文学研究科・国際フォーラム「京都から世界へ-知の次なる一歩」を開催した。文 学研究科としては希有の試みであった。
このフォーラムは、長尾真総長より文学研究科に国際シンポジウムの勧めがあり、それを受けて文学研究科では、「日本の文化拠点たる京都という磁場を背景 に、本研究科でなされている人文学研究の現在と将来の展望とを世界に発信する」という基本コンセプトを据え、文部科学省(国際シンポジウム経費)、京都大 学教育研究振興財団、京大以文会より資金援助を受け、共催:京都新聞、京都府・京都市・NHK京都放送局・京大以文会の後援を受けて開催された。参加者 は、京都大学の出身者に限らず老若男女さまざまな顔ぶれであり、800余名を数え、極めて盛会であった。
当日は、総長、文学研究科長の挨拶のあと、ハーヴァード大学ジョン・ローゼンフィルド名誉教授が「日本文化の転生-重源の事跡」の演題で講演された。つい で、元京都大学文学研究科・現放送大学柏倉康雄教授を司会として、イェール大学ヴァレリー・ハンセン教授、北京精華大学葛兆光教授、京都大学医学部長中西 重忠教授、京都大学文学研究科佐々木丞平教授、同伊藤邦武教授、同内井惣七教授がそれぞれ最新の研究成果を話されたあと、ジョン・ローゼンフィルド名誉教 授を加えて、「研究することの意味、あるいはそのおもしろさ、そしてそれを世界に向けて一体どういうふうにして発信していくのか、社会に還元するのかと いった課題を中心」にシンポジウムが行われた。
なお、このフォーラムの記録冊子『京都から世界へ-知の次なる一歩』(非売品)が同年11月に刊行されている。また、このフォーラムの意図とほぼ同一線上 で、文学研究科の教官を中心としたエッセイ集『知のたのしみ学のよろこび』を2003年に岩波書店から京都大学文学部編で刊行した。
21世紀COEプログラム
2001(平成13)年6月の「大学(国立大学)の構造改革の方針」に基づいて「活力に富み、国際競争力のある国公私立大学づくりの一環として、「世界最 高水準の大学づくりプログラム-国公私「トップ30」-」が、構造改革特別要求の予算枠で設けられることになった。国公私「トップ30」の名称は、さまざ まな批判を呼び、2002年はじめには、「世界的教育研究拠点の形成のための重点的支援-21世紀COEプログラム-」と変わった。
文学研究科でも、このプログラムに申請すべく取り組み、最終的には文学研究科のほぼ全専攻で構成された「グローバル化時代の多元的人文学の形成」(拠点 リーダー:紀平英作)と、文学研究科の心理学専修を核に教育学研究科、人間・環境学研究科、情報学研究科の心理学関係の専攻とが組織した「心の働きの総合 的研究拠点形成」(拠点リーダー:藤田和生)、を申請し、2002年10月9日採択された。
このプログラムは、5年を基本期間としたもので、2年経過した後に中間審査を受けることとなっていたが、幸い2プログラムとも審査を通り、現在も進行中で ある。
オープンキャンパス
2002(平成14)年、全学的取り組みとして、オープンキャンパスが実施されることになった。2002年は、8月8日と9日の両?に開催され、両日とも 午前中、総合体育館において全体説明会があり、8日午後は文系学部と理学部、9日午後は医学部・薬学部・工学部でそれぞれ会場を分けて開催された。文学部 では、ABの二つの時間帯に分け、それぞれに180名の希望者を募り、新館第3講義室を会場に、学部長の歓迎の挨拶のあと、各系ごとに施設見学、研究室訪 問を実施し、最後に分野別教官との意見交換をもって終了した。
2003年は、8月11日に「みやこめっせ」を会場として、総長の講演、在学生からのメッセージのあと午後は相談コーナーでの相談にあてられた。12日、 文学部では、午前と午後の2回に分け、それぞれ200名を限り、新館第3講義室を会場に、歓迎の挨拶、各系の説明と参加者との質疑応答がなされたあと、系 ごとに施設見学、研究室訪問が行われた。
2004年は、8月17日18日の両日があてられ、両日とも午前は時計台百周年記念ホールで全体説明会があり、文学部は17日の午後に2回の説明会を開催 した。内容は、歓迎の挨拶、文学部紹介ビデオ、各系の説明、系ごとの施設見学、研究室訪問、ミニレクチャー、質疑応答で構成された。これとは別に学部質 問・相談コーナーが新たに設けられた。2005年は8月11日12日の2日、文学部は11日に前年同様の形式で行われた。
法人化と文学研究科
法人化への準備は、2001年に入って始まる。同年12月には、文学研究科中・長期計画策定ワーキング・グループによって作成された「あるべき今後の文学 研究科像について-あたらしい「人文学」にむけて-」が提案され、12月20日の教授会で、中・長期計画の最終案として承認された。
本案は、はじめに、1.基本理念、2.長期目標、3.各専攻の将来像、付記とからなる。1.基本理念では、1. 文学研究科における教育研究は、「人間とはなにか」を問う、2. 「人類文化」の探求のため、多様な学問分野の共通の土台となる基礎学・普遍学としての「人文学」を多角的に研究し、あわせてそれらの総合化をめざし、3. 学問における「伝統の継承」を重要な役割とし、4. 長期的構想のもとで真理を探究し、5. 人類文化の継承と地球社会の持続的発展に寄与し、真に新しい知の創造の源となることを掲げている。
2002年3月20日、自己点検・評価文学部委員会の下に、「文学研究科中期目標・中期計画作成ワーキング・グループが設置された。同年7月10日の教授 会において、文学部・文学研究科「中期計画・参考資料」(第1次案)が承認された。その後、大学全体の中期目標・中期計画のワークシートが提示され、それ に沿った文学研究科・文学部の第1期「中期目標・中期計画」[大学実施要項]を作成し、2003年7月、本部に提出した。
このワークシートは、I 中期目標の期間、II 部局としての基本的な理念・目標、III 部局等の教育研究等の質の向上に関する目標と目標を達成するために取るべき措置、の3部構成である。IIに示された基本理念は、以下の通りである。
文学研究科は、明治39年(1906年)、京都帝国大学文科大学として開設されて以来、学問それ自体の要求する実証性に即して研究教育の体制を築くことを 理念として常にかかげてきた。これはまた京都大学全体の中心にある自由と自主の理念そのものでもある。本研究科の特色である高度で厳密な実証主義の伝統 は、わが国の伝統文化の中心地である京都に位置するという立地条件ともあいまって、本研究科を人文系研究教育の世界的な拠点のひとつとして既に広く認知さ せるに至っている。そこで文学研究科は、京都大学全体の基本理念を踏まえ以下の基本的な理念をかかげるものである。
- 文学研究科は、人間の根源的な価値を再び確立し、広く世界に示す研究と教育を行う。
- 文学研究科は、万学の基礎学としての人文学を探求し、人類文化全般の意義を総合的に明らかにすることをめざす。
- 文学研究科は、学問における伝統の継承を重視し、実利に偏することも虚学に甘んずることもなく、長期的構想をもって真理の探究 を行う。
- 文学研究科は、人類文化の継承と地球社会の持続的な発展に寄与し、真に新しい創造の担い手となる人材を養成すべく研究と教育を 行う。
- 文学研究科は、急激な変化をともなって展開する現代の地球社会の実相を真摯に把握し、時代のあるべき人文学の創造をめざす。
文学研究科は、こうした理念をかかげて、2004年4月、国立大学法人京都大学のもと新たな船出をするが、順風満帆というにはほど遠く、多くの新たな問題 を抱えることになる。その最大の案件は、2003年度を基準として毎年1%の効率化係数が、人件費にも物件費にもかけられることになったことである。文学 研究科に単純に当てはめれば、教員1名の削減を毎年行わなければならないことになり、これまでの文学研究科の教育研究体制を大きく揺るがしかねない問題で ある。もう一つの案件は、2004年度以降、これまで認められてきた非常勤講師経費が財務省で予算化されなかったことにより、その経費を研究科で負担する 必要が生じたことである。このように、法人化は、文学研究科の研究・教育にとって望まれるものとはいいがたい。
文学部百周年記念事業
2006年の文学部百周年にあたり、京都大学文学部百周年記念事業会が結成され、卒業生・教員等からの募金を募り、以下のような事業が計画されている。
第1は、記念式典である。式典は、2006年6月10日、京都大学時計台記念館百周年記念ホールにて執り行ない、あわせて、ジョシュア・フォーゲル教授、 マイケル・ヴィッツェル教授、上田閑照名誉教授による講演会が企画されている。
第2は、記念論集『グローバル化時代の人文学』(仮題)と『京都大学文学部の百年』の刊行である。前者は、文学研究科における活動の最新の成果を反映しよ うとするものである。後者は、本書であり、卒業生・教官執筆にかかるエッセイ、文学部・文学研究科百年の歴史、専攻・専修の歴史等で構成される。
第3は、「文学部・文学研究科教育支援基金」の創設である。これは、家庭の事情等で学業の継続が困難となった学生への支援を目的とするものである。第4 は、学生が憩える環境整備である。文学部周辺に植樹したり、休息室等を設置することが計画されている。
第5は、文学部所蔵の図書の修復である。文学部では創設以来、研究・教育のために核となる書籍を収集してきたが、その数は現在91万冊の多きに達し、その なかには極めて貴重なものが多くあり、また百年近いあいだに虫損や劣化による損傷もみられるようになり、修復しなければ利用することができないものも出て きた。本事業は、これに応えるものである。
募金額の目標を3000万円としたが、2006年3月現在で、2650万円を超え、多くの方々の協力が得られ、事業はほぼ目標どおりに進められるであろ う。